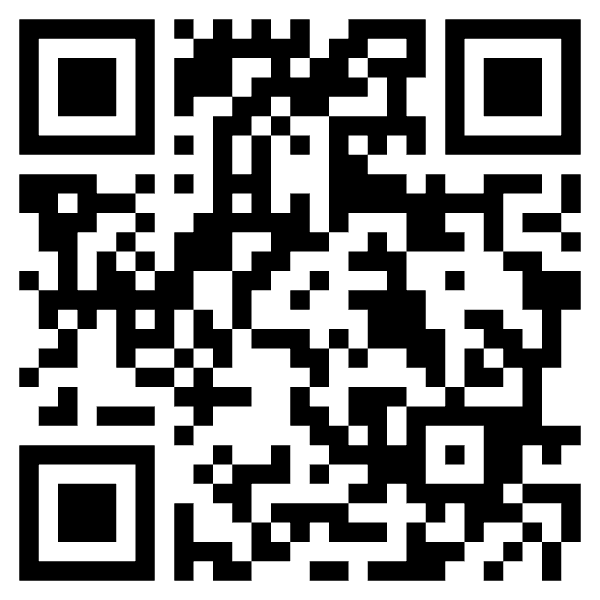【高松宮記念杯競輪】どっちが強い!? 競輪界唯一の東西戦 ポイント制予選勝ち上がりのカギは
アプリ限定 2025/06/06(金) 12:00 0 17
6月17日から前半戦最後のGI「高松宮記念杯競輪」が開幕する。2023年大会からガールズケイリンGI「パールカップ」新設に伴い6日制となった。ここでは高松宮記念杯の選考と、一次予選がポイント制で準決勝が4レースという特殊な勝ち上がりルールについても解説する。
競輪界唯一の東西対抗戦
6月17〜22日に岸和田競輪場で開催される「高松宮記念杯競輪(GI)」。4月下旬に出場選手が発表された。
1950年から続く歴史ある大会で、1973年から今まで競輪界で唯一の「東西対抗戦」として行われているのが大きな特徴だ。
出場選手選考の時点から、東西に分かれて選抜される高松宮記念杯競輪。まずは選考条件から見ていこう。
【高松宮記念杯競輪 選考条件】※開催時S級
(1) S級S班在籍者
(2) 過去3回以上優勝した者(開催時S1)
(3) パリ五輪自転車競技トラック種目代表選手
(4) 東西別平均競走得点上位者(同点の場合は選考期間における選考用賞金獲得額上位者)
※選考期間は2024年10月〜2025年3月の6か月
ポイントとなるのは(4)の「東西別平均競走得点」だ。競輪選手の“強さ”の指標として用いられる平均競走得点が重視されるため、比較的妥当なメンバーが揃う可能性が高い。
高松宮記念杯競輪における「東西」は、以下の通りに分けられている。
| 東西 | 地区 |
|---|---|
| 東 | 北日本、関東、南関東 |
| 西 | 中部、近畿、中国、四国、九州 |
都道府県別出場選手数は?
決勝まで東西に分かれての勝ち上がり戦となるため、同地区の別線勝負もたびたび目にする。ここでは都道府県別の出場選手数を見ていきたい。
東日本
| 出場選手数 | 都道府県 |
|---|---|
| 8 | 神奈川 |
| 6 | 宮城、福島 |
| 5 | 茨城、栃木 |
| 4 | 埼玉、千葉 |
| 3 | 群馬、東京、静岡 |
| 2 | 青森、岩手 |
| 1 | 秋田、長野、新潟 |
※北海道、山形、山梨は0
西日本
| 出場選手数 | 都道府県 |
|---|---|
| 5 | 岡山、熊本 |
| 4 | 岐阜、奈良、徳島 |
| 3 | 三重、京都、大阪、愛媛、長崎 |
| 2 | 愛知、福井、和歌山、山口、福岡、佐賀 |
| 1 | 兵庫、広島、香川、大分、沖縄 |
戦力の厚さが目立ったのは、神奈川県だ。前年覇者が不在でも郡司浩平、松井宏佑をはじめとした選手たちの奮闘により勢力を伸ばし続けている。
西日本は大混戦だ。1位タイは太田海也擁する岡山、嘉永泰斗擁する熊本で5人が出場する。意外にも古性優作、南修二ら強豪揃う地元・大阪勢は3人止まりという結果に。
東西どっちが強い?
結局のところ東西強いのはどちらなのか? そんな疑問を抱く方も多いだろう。そこで過去75大会の優勝者を調査したところ東が40勝、西が35勝とやや東が優勢だ。
しかし直近10年では東西共に5勝ずつと拮抗しており、東西の差はほとんどないものと考えていいだろう。
直近10年優勝者
| 東 | 西 |
|---|---|
| 武田豊樹(2015年) | 三谷竜生(2018年) |
| 新田祐大(2016年) | 中川誠一郎(2019年) |
| 新田祐大(2017年) | 脇本雄太(2020年) |
| 宿口陽一(2021年) | 古性優作(2022年) |
| 北井佑季(2024年) | 古性優作(2023年) |
地区別の直近10年成績を見てみると近畿勢が4勝で断トツ、中でも地元の古性優作は22年、23年で連覇を果たすなど、ホームの利を活かした活躍を見せている。
高松宮記念杯出場選手の競走得点
高松宮記念杯に出場する選手の、直近の競走得点はどうだろうか? 6月4日時点での点数で比較してみた。
まず出場選手の平均は110.58点と日本選手権競輪の108.56点、ウィナーズカップの108.45点と比較すると約2点ほど高い。
個人ではもっとも点数が高いのが古性優作で121.57点、次点の郡司浩平が117.61点とこの両者で4点近くもの差がある。いかに古性が圧倒的な地位を築いているかが分かるだろう。
選考条件が競走得点のために極端に点数の低い選手はおらず、100点未満の選手はゼロ。最も低い寺沼拓摩でも103.1点という最下位にしてはかなり高い部類の点数を持っている。
波乱も起こりうるポイント制
高松宮記念杯は2023年から6日制になり、一次予選がポイント制となった。特選などのシードレースはなく、S班を含めた全員が一次予選を2走して勝ち上がりを競う。
| 着順 | 一次予選1 | 一次予選2 |
|---|---|---|
| 1着 | 10pt | 13pt |
| 2着 | 9pt | 11pt |
| 3着 | 8pt | 9pt |
| 4着 | 7pt | 7pt |
| 5着 | 6pt | 6pt |
| 6着 | 5pt | 5pt |
| 7着 | 4pt | 4pt |
| 8着 | 3pt | 3pt |
| 9着 | 2pt | 2pt |
| 棄権 | 1pt | 1pt |
| 失格・欠場 | 0pt | 0pt |
4着以下のポイントは1走目も2走目も同じだが、確定板に入ることの価値は2走目の方が大きくなっている。
先述のとおり東西に分かれたトーナメントになっており、西日本のポイント上位9名は4日目11Rの白虎賞、東日本のポイント上位9名は4日目12Rの青龍賞に進む。この2レースは準決勝フリーパスである。
昨年の一次予選ポイント結果を見てみると、勝ち上がりボーダーは以下の通りだった。同点の場合は選考順位により序列される。
| 結果 | 東日本 | 西日本 |
|---|---|---|
| 優秀競走 (青龍賞・白虎賞) | 23〜20pt | 23〜17pt |
| 二予進出 | 19〜10pt | 17〜10pt |
| 選抜回り | 10〜5pt | 10〜5pt |
※連勝すると23pt、9着2回で4pt
シード戦へのボーダーはやや東日本の方が高いものの二次予選ボーダーは東も西も10ptという結果だった。シード戦に進むためには2日連続の連対がほぼ必須となる。二次予選ボーダーは10ptと一度確定板に入ることが出来ればある程度勝ち上がりは安泰なラインとなっている。
しかし23年、24年共に10ptのボーダー上では泣き別れが発生しているため、選考順位が低い選手は1ptでも多く稼いでおきたいところだ。
一発勝負ではなく2レースを走っての合計のため基本的には上位選手が順当に勝ち上がりやすいポイント制だが、昨年は清水裕友が危うく敗退の危機に陥るなど波乱が起きる可能性も大いにあり得る。
準決勝は激戦必至の4レース
東西合わせて準決勝が4レースあるのも高松宮記念杯の大きな特徴といえるだろう(通常は3レースで上位3名が決勝進出)。
そのため準決勝から決勝への勝ち上がりが厳しい。確実に決勝に進めるのは2着までの8名で、残りの1枠は東西準決3着の4名のうち1名だけだ。前走の着順でワイルドカード1名が決まるが、青龍賞・白虎賞に出場した選手が優先となる。
昨年の決勝で準決3着から決勝に進んだのは新山響平(青龍賞4着)。ほかの3名は諸橋愛(東二次予選3着)、犬伏湧也(西二次予選1着)、山田久徳(白虎賞4着)だった。山田は新山と同じく前走シード戦4着だったが、予選のポイントで新山が山田を上回ったため新山が決勝へと進む結果となった。
GP切符3枚目は誰の手に
前半戦最後のGIとなる「高松宮記念杯競輪」。3日目まではガールズGI・パールカップが並行して行われ、男女それぞれ年末のグランプリ出場選手が決まる。
残されたグランプリの切符は残り7枚、岸和田の熱い大歓声の中優勝のゴールを駆け抜けるのは一体誰になるのか。ぜひ注目してほしい。
※6/13 17:40 都道府県別出場者数を修正しました